都立西高OB吹奏楽団 風林火山〜NOBB 29th〜
 pray |
松雪泰子のデビューアルバム。この他にも数枚のアルバムやシングルが発売されているが、この一作目が最も出来がいい。曲も聴きやすく良質な楽曲ばかりである。彼女の音楽面に触れてみるなら、取りあえずこのアルバムから入ってみてはどうだろう。 |
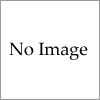 天平の甍 [VHS] |
東京国立博物館で開催された「唐招提寺展 国宝 鑑真和上像と盧舎那仏」2005年1月12日(水)~3月6日(日) で、この映画の上映がありました。 仏教の教えを日本にいきわたらせる目的で中国から高僧を招くために、日本の若き僧が中国に渡る。鑑真和上に出会い渡日の承諾を得るまでに10年近くを費やし、その後成功するまでに11年6回の企て。この時代のこのプロジェクトは、現代でいえばアポロが月の石を持ち帰った快挙に近いかもしれません。 結果的に僧の一人普照は目的を達しましたが、途中で別の道に歩んだもの、病で命を落としたもの、30年以上の労作とともに海の藻屑と消えたものの姿も描かれます。必ずしも報われない”10年がけの執念”が凝縮されて、唐招提寺として今に伝えられていることに素直に感銘をうけました。こういったストーリーをふまえて見る古い寺院や像は、実に生々しく立体的でした。 こうやって人類は一歩一歩進化してきたのですね。報われるか報われないかを考えていたらできないことです。この映画も、ビデオ/DVDとして伝えていってほしいと思いました。 |
 氷壁 [DVD] |
近くのレンタルショップを何軒も探したのですが見付からずネットレンタルでみて、すごく良かったのでDVDを購入しました。
とにかく山の迫力のある映像とリベラの透明感のある音楽も良いのですが、それに負けないくらい主演の玉木宏さんがすばらしいです。あまりにも美しいシーンの連続で見入ってしまいました。のだめの千秋以上に男らしくて美しい玉木さんが堪能できます。共演の役者さんたちもすてきなので、玉木ファンには絶対おすすめ!必見です。 お話はなんの知識もなくてみるほうが楽しめると思います。初めてみた時は、次はどうなるんだろうと毎回ドキドキでした。映画のような美しいシーンがいっぱいのこんな良い作品が多くの人に見られていないのはとても残念です。ぜひ再放送してほしいです。 |
 トキオ 父への伝言 [DVD] |
東野圭吾さんのタイムトラベル物の名作を原作に、NHKが15分×全20回で放送したドラマ。
「悪くない」と思いましたよ。原作はとても好きなだけに映像化されてがっかりだけはしたくなかったのですが、国分太一さんの50歳はどうもなぁとか、妻との出会いは原作の方が好きだなぁとか、粗はあるのですが満足できるレベルでした。敢えて妻との出会いを原作から変えたのは「父への伝言」の副題のとおり、トキオと拓実の父子の物語だという所にフォーカスをあてたかったからでしょう。「父への伝言」は原作にはない部分で、原作ではタイムトラベルしたトキオの思いは抑えめだったので、小舟でのビールを飲み交わすシーンや祖母とのシーンでトキオの物語を演出していたのは見事だと思いました。 15分物のドラマでは勿体ないなぁというのは、ウチも思いました。1時間×2の方がいいんじゃないでしょうか。 あと、DVDには特典映像やキャストを紹介するコンテンツもなくていかにもNHKなのですが、もう少しサービスが欲しいなぁと感じました。その点はお得感がないので、☆半個分くらいは下げたい気分です。 |
 茶々-天涯の貴妃(おんな)- 通常版 [DVD] |
戦国時代で最も数奇な運命を辿った事で有名な(浅井三姉妹)。本作は長女・茶々のお話です。 彼女は戦略結婚させられた信長の妹・お市と浅井長政の娘として産まれ,叔父・織田信長に父を討たれ,市の美貌を一番受け継いだ為に,市に恋をしていた豊臣秀吉に目を掛けられ,秀吉の側室として嫁ぐなど,まるでお伽話のような人生を歩んだ女性です。茶々にとって平穏な日々は無かったのではと思います。戦国時代を生きる為に戦を恐れぬ逞しい女性ですが,同時に悲劇の運命を辿った悲しい女性でもあります。 三姉妹は幼い頃から助け合い,誰よりも強い絆で結ばれていたのですね。もし時代が違っていれば,どれだけ笑いあい,楽しい人生を過ごす事が出来たでしょう。戦とは美談ではなく,家族の絆すらも奪ってしまうのです。こんな悲しい事はあってはなりません。 余談ですが,和央ようかさんの男装姿はさすが!!と思わせる程美しいです。個人的にはソコも見所と感じています。 |
 おろしや国酔夢譚 (文春文庫 い 2-1) |
大黒屋光太夫を主役に据えた時代小説。
彼と部下16名の漂流は無論史実であるものの、本書は記録小説ではなく、 井上靖作品らしいテーマをもって描かれた、人間ドラマと言っていい。 井上作品には、強烈な「生きるよすが」を持っている人物が数多く登場するが、 本作における光太夫もまさにそういった人物として描かれている。 その「よすが」は言うまでもなく「生きて故国の土を踏む」という一点。 酷寒の大地の上で、彼は決然とその日を信じて、前を向いて生きてゆく。 しかし本作における主人公は光太夫だけでなく、おそらく漂流民16人全員だろう。 帰国する者、ロシアに残る者、そして死んでいった仲間たち。 はじめ想いを一つにしていたはずの彼らも、いずれ運命はそれぞれの方向を向き、 別々の道へ向かって行かざるを得ない。 ”人間はそれぞれ独立した存在であり、心も体も、絶対的に孤独なものなのだ” 交錯する彼らの運命から、井上氏はそれを伝えたかったに違いない。 そして10数年の流浪の末に光太夫がたどり着いた場所で見たもの。 人の心の置き場とは一体どこにあるのか? すべてが一酔の夢であったかのような彼の人生が、読者の胸に余韻を広げる。 |
 敦煌 (新潮文庫) |
敦煌から約25km,鳴沙山の斜面に莫高窟はある。
1900年,長く埋もれてきたこの遺跡から夥しい数の文献が発見された。 やがて本格的な研究が進んでゆくに従い、それが世紀の大発見であることが判明してゆく。 貴重な経典の数々が含まれていたことはもとより、それを記す文字にも多彩なものが含まれていた。 西夏文字もその中の一つだった。 本作は11世紀初頭の西域を舞台として描かれた歴史小説。 史上の人物である李元昊や曹兄弟などは脇役であり、趙行徳・朱王礼・尉遅光など架空の人物が縦横に動かされ、 それぞれの個性が絡みあってダイナミックな物語が展開してゆく。 大きなモチーフに「文字」があると感じた。文字は人間の歴史を語り、後世に伝えて行くものである。 西域には雑多な民族が勃興しては滅んで行ったが、文字による記録を残したのはそのうちの僅かに過ぎない。 それを残さなかった者たちは何も語らず、ただ遺跡と人々の記憶が僅かに彼らを呼び返すのみである。 新興の西夏は「西夏文字」を生み出した。行徳はその文字を学ぶために西域を目指した。 朱王礼は自らの戦いの歴史を刻むために、行徳に碑を建てることを命じた。 彼らはそれぞれ後世まで自らの生を「文字」で伝えたかったに違いない。 一方ウイグルの女は、何も語ることなく城壁から身を投げ消えてゆく。 彼女の面影はただ行徳や王礼の記憶の中にあり、それぞれの中で別々の姿を残してゆく。 行徳は仏教に傾倒し、王礼は深く復讐の思いを秘める。 彼女の本当の思いがどこにあったのか、それは謎のままに。 記録と記憶の狭間で、人々は存在の本質を問う。 それは一人ウイグルの女に言えることだけでなく、歴史の営みそのものにも当てはまる。 多くの歴史が交錯した西域は、それを最も雄弁に物語る舞台と言っていい。 時代と舞台、そして人物。この敦煌は、それらが融合して織り成す壮大な詩である。 |
 現代語訳 舞姫 (ちくま文庫) |
「舞姫」は「うたかたの記」「文づかひ」とともに、二十代の鷗外が、自らのドイツ留学体験をもとに書いた、痛切な青春小説である。文語文で語られたその「雅文体」は、たとえようもなく美しいだけでなく、回想に適した文体でもあるので、「現代語訳」には違和感がないわけではない。だが井上靖の訳文(1982年)は、崩れのない端正な現代日本語になっている。たとえば、はじめて恋人エリスに会うところ。「今この処を過ぎんとするとき、鎖(とざ)したる寺門の扉に寄りて、声を呑みつつ泣くひとりの少女(をとめ)あるを見たり。年は十六、十七なるべし。かむりし巾(きれ)を洩れたる髪の色は、薄きこがね色にて、・・・この青く清らにて物問ひたげに愁ひを含める目(まみ)の、半ば露を宿せる長き睫毛に覆はれたるは、何故に一顧したるのみにて、用心深き我が心の底までは徹したるか。」
それがこう訳される。「今この所を通り過ぎようとする時、鎖(とざ)したる寺門の扉にもたれて、声を呑んで泣く一人の少女が居るのを見た。年は十六、十七であろう。被ったマフラーからこぼれている髪の色は薄いこがね色で、・・・この青く清らかで、もの問いたげに愁いを含んでいる目の、半ば涙を宿している長い睫毛に覆われているところなど、どうしてひと眼見ただけで、用心深い私の心の底にまで焼きついてしまったのであるか。」(p23)つまり、原文に近い訳なのだ。原文が付いているので、訳文との日本語の90年の”時差”について色々と考えさせる。関連資料も豊富で、義妹の回想では、鷗外を追って来日した実在のエリスに森家が慌てた様子が面白い。ベルリンという都市空間から見た前田愛の「舞姫」論や、それを受けた神山伸弘のベルリン考証など、多面的に「舞姫」が鑑賞できる。 |


![Babel [バベル] - Ep1 part 1 バベル](http://img.youtube.com/vi/7JOzhPGZigE/3.jpg)






