 Henckels ローマ 片手鍋 16cm 40365-160 |
今まで百均で買った片手鍋を使ってましたが、なんとなくデザインに惹かれて購入。
しっかりした片手鍋で一人暮らしの自分になんとも重宝するサイズ。熱伝道がいいってこういうことなんだな、と実感。買って正解でした。 |
 3大テノール 世紀の競演 |
お三方ともすばらしい歌声なのですが、あまり心に響いてこなかった。自分でも意外に思えました。声、技巧とも全くすばらしいのですが、心がこもっているようには聞こえなかったです。3人で競い合っていたのか、自己主張が歌声に入ったのではないでしょうか? |
 ア・デイ・ウィズアウト・レイン |
とにかく始まりのインスツルメント曲(アルバムタイトル曲)がいいですね。
雨が降らない穏やかな一日、これは人生の雨風をくぐり抜けた穏やかな日々 とも取れます。若い日々の緊張感から解き放たれた解放感を感じます。 中年にさしかかり、そしてこれからも同時代を生きてゆくのは変わりないけれど 一旦そこで荷物をおろして、これから歩む道を肯定的に見ているように思えます。 自分を肯定しこれから先も、様々な困難もあるかもしれないけれど肯定的に生きる ことを応援してくれているように感じます。 もしかしたら、このときエンヤは遠い先の「死」というものも、意識しているの かもしれない。それは誰にもわかりませんが、この楽曲から感じることはそれらも 含めているような感じがしたのです。あくまでも自分の感じですが。 |
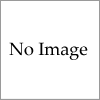 ローマ帝国の滅亡 [VHS] |
ストーリー-は、最後の五賢帝マルクスアウレリアスの死後のローマの混乱を描いたもので、数年前映画化された、「グラデイエーター」と同じ設定。 あの映画でも出た、コモドゥスやルキラ他実在した人物も出てきます。 時代がかったまるでギリシャ古典劇のような科白まわしなどは気になりますが、驚かされるのは40年前に作られ、殆どCGなどが使われていないということ。 戦車での戦いや様々な合戦シーン、決闘シーンなど見どころが沢山あります。 そしてソフィアローレンの妖艶さ。 当時は衣料や小道具の技術も発達してなかったから、重い甲冑を担ぐ俳優さんたちや馬は大変だったでしょう・・・ ただ、コモドゥス帝の俳優よりリビィウスの俳優の方がどうしても悪人顔に見えてしまうので反対だったらよかったかもしれません。 本当にこの映画を製作するのは大変だったとしみじみ感じます。 |
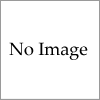 ローマの休日 製作50周年記念 デジタル・ニューマスター版【字幕版】 [VHS] |
ローマを訪れた小国の王女アンは、行事ばかりの退屈な毎日にうんざりしていた。不満を訴える王女に、主治医は気持ちを落ち着かせるために鎮静剤を注射する。とうとう夜中にこっそり大使館を抜け出した王女だが、鎮静剤が効いてきて道端で眠り込んでしまう。そこに通りかかったのが、アメリカ人の新聞記者、ジョー・ブラッドレー。仕方なく彼女を自分のアパートに泊めた翌朝、会社に出勤したジョーは、そこで新聞のトップを飾るアン王女の写真を見て驚愕した。アン王女と、昨晩家に泊めた女性が瓜二つなのだ。・・・ 退屈な王室を脱け出して、美容室で長かった髪をばっさり切ってみたり、ソフトクリームを買って広場の石段に座って食べたりして、開放された自分だけの時間を楽しむ王女のオードリーが、本当に愛らしいです!喫煙、オートバイの2人乗り、名所の「真実の口」に願い事を叶える壁、そして船上パーティーでのダンス…。時にははちゃめちゃながらも、ローマでの時間を楽しむ王女とジョーが素敵です。オードリー・ヘプバーンの気高いまでの美しさ、グレゴリー・ペックの渋めのハンサムぶりと相成って、心が通いながらも身分の違う叶わぬ恋にホロリとさせられました。ラストに号泣しつつも、流れる涙が暖かく感じる作品です。まさに名作といえる作品だと思います。 |
 ローマの休日【字幕版】 [VHS] |
この間、初めてローマの休日を見た。 オードリヘップバーンも可愛いし、グレゴリーペックもすごくかっこいい。心が少しずつ通いはじめる初々しさが大変によい。 テレビの前で、両手を手に膝で前に前にのにじり寄って行ってしまいそうな感じ。 最後のシーンで、グレゴリーペックがオードリヘップバーンにインタビューするところがこれまたよし。 映画自体が若干古いだけに、英語がきれい。 |
 ローマの休日 製作50周年記念 デジタル・ニューマスター版 [DVD] |
大学生の卒業旅行先としても大人気のイタリアのローマ。その中でも『ローマの休日』を鑑賞してローマ、イタリアの虜になった人も多いはずです。「妖精」と謳われるオードリー・ヘップバーンを最もよく現しているのがこの作品だと思います。アン王女(オードリー)は公務に嫌気が差して、宮殿を出ます。ふと街角で出会うのは新聞記者ジョーブラドリー(グレゴリー・ペック)。この日、二人はローマを散策します!べスパに乗ったり、美容室でのヘアーカット、真実の口・願いの叶う壁に行ったり。。。。と。
色んな見所はあるのですが、私が一番注目したのは「ひとときの愛」です!王女と新聞記者。身分の違いがあり、ずっと身を共にすることには無理があります。だけど、ローマで過ごした半日に至福の瞬間を感じました。それは最後の記者会見で、アン王女とジョーがずっと数秒、目でお互いの意思・決意を確認したシーンで納得しました。 ただ、ローマの休日の映画のみを鑑賞したい人にはもっと安価なDVDが発売されていますが、ローマの魅力を含めた特典ディスクをも堪能した人には、本作品は非常に価値があると思います!! |
 ザ・ローマ 帝国の興亡 DVD-BOX |
以前発売された、「ガーディアン ハンニバル戦記」で「これはいける」とわかったのか、今度はドイツのZDF、アメリカのディスカバリー・チャンネルも巻き込んで、BBCが制作したドラマ。
アカデミー賞受賞作「クイーン」にてブレア首相を演じたピーター・ジーン、「28週間後」、「サウンド・オブ・サンダー」に出演しているキャサリン・マコーマック、英国の長寿SFドラマ「ドクター・フー」で第三代ドクターを演じたジョン・パートウィーの息子、ショーン・パートウィー、そして、シェイクスピア役者でもあり、「戦争のはらわた」でも有名なベテラン、ディビット・ウォーナー等、英国のテレビ、映画、演劇界の実力者達が主演している。 ローマ”帝国”500年の歴史のうち、詳細で確実な資料が残っており、尚且つローマという「世界帝国」を理解するキーとなる出来事をピックアップし、エピソード化したのが本作である。 それらは、各エピソードの時代が大きく離れていることからも伺える。第1話のカエサルや、第2話のネロは当然としても、第4話の共和政期のグラックスの土地改革は、「当時は共和政でしょう?帝国は関係ないんじゃないの?」という疑問を持たれる方もおられるかもしれない。だが、見ていただければ、なぜこれを「帝国の興亡」のエピソードに組み込んだかがよく理解できることだろう。そしてそれは、中華帝国とは全く異なる、ローマ帝国の特色を理解することでもあり、ひいてはヨーロッパを理解することにもつながるだろう。 ドキュメンタリー・ドラマと銘打ったこれらは、冒頭でも、「史実」のみしか取り扱わない、即ち、架空の人物や架空の出来事を描くことはしないと宣言しているが、「ドラマ」でもある以上、多少、経過を省略したり、センセーショナルで、存在が疑問視されている事件を混入したりもしている。 例えば、第1話「カエサル」において、彼が実際に第9軍団を「十人一殺刑」に処したかは疑問の余地がある。また、第3話「反乱」において、エルサレム興亡に当たっての傾斜路建設と、攻城塔投入に関するユダヤ側の反撃が、ドラマの中ではただ一度のシーンにまとめられている。それに、第4話「革命」においても、グラックスはカルタゴ攻略には参加していないが、彼が城壁冠を得たのはカルタゴ市の攻略戦として描かれている。 これらは、「ドラマ」である以上は仕方のない部分であるが、それでも、美術、衣装にこだわり、当時の社会情勢もおりこんで描かれたこれらのエピソードは、恐らく映像化は初めてと思われる第一次エルサレム攻防戦、意外と映像化されているようで日本への紹介は少ないコンスタンティヌスの権力掌握過程、ティベリウス・グラックスの土地改革が引き起こす混乱、西ゴート王国の祖、アラリックのローマ劫掠(スティリコも短いながら登場!)等、カエサル、アウグストゥスだけではない、ローマ帝国の様々な姿を見るものに印象付ける、良質のエンターテイメント作品となっている。(勿論ドキュメンタリーとして見た場合、理解のしやすさは一級品である) また、少しマニアックな着眼点だが、オスプレイ社刊行の図解のファンのかたがたならば、時代ごとに違うローマ軍の甲冑、装備に着目し、そのこだわりに唸らされることだろう。正確な考証に基づくロリカ・セグメンタータとガリア型兜を被った一世紀のローマ兵(第3話)、インテルキサ型兜とスパタの四世紀のローマ兵(第5話)など、これもまた、映像化されていそうでいなかった姿を見ることが出来る。 カエサルとクレオパトラだけがローマではない、と言うことを実感させてくれるエピソードばかり。ローマ帝国に興味があるならば、必ず一度は見てみるべきである。 |
 シャドウ・オブ・ローマ カプコレ |
うーん・・・気持ちの上では星5つあげたいのですが、どうしても手放しで勧めることはできません。
まず、メインとなるアグリッパのアクションパートですが、色々考えてやる割には作業感が強く、全体的にもっさりとしています。 それぞれの武器の役割がはっきりしているのが逆に仇となって、使う状況が自ずと限定されてくるため、期待していたほどの自由度はないです。 難易度もかなりシビアなものとなっているので、効率的なプレイをしないと、クリアもままなりません。 操作も、慣れるまでは若干クセがあります。 ひたすらやりこんで、「こうやるんだ」という手順(大体誰もが同じところに行き着くと思います)を発見するゲームです。 自分の地道なプレーによる上達を楽しめる人には、かなり歯ごたえのあるゲームですが、並み居る敵をバサバサと切り倒す分かりやすい爽快感を求めている人には、全く口に合わない作品になると思います。 良くも悪くも、前時代的な作りのゲームです。 サブとなるオクタビアヌスの探索パートは、やることが逐一決まっているので、仕掛けを理解してしまえば、二度とやる気が起きません。 ただ、一回殴られると即座にゲームオーバーなので、振動パックを使った心音の演出も手伝い、味わえる緊張感は本物です。 他のレビューにも見られるとおり、昨今では珍しいくらいに硬派な作りをしており、個人的にはとても好感が持てます。 ただ、よく出来ているがゆえの煩雑さのようなものが邪魔をして、一般にはかなり受けが悪いであろうゲームです。 勿論、ガチゲーマーの人にとっては、垂涎モノの名作であろうことは疑う余地もありません。 リアルタイムレンダリングのイベントシーンは、人間の表情や口の動きまで細やかに作りこまれていて、大変美麗です。 PS2のタイトルに限定すれば、ことグラフィックの美しさについては、一番と言っても差し支えないと思います。 古代ローマの壮大な世界観が伝わってくる魅力的なビジュアルも目を惹きます。 色々と難を挙げておいてなんですが、これで2000円ならお釣りがくると思います。 |
 ローマ亡き後の地中海世界 下 |
まず、(上)刊行から約1ヶ月で(下)が刊行されたことを嬉しく思う。そして2冊を一気に書き上げた著者のエネルギーに敬服する。
本書はオスマン・トルコの台頭からレパントの海戦に至る歴史を大きな視点で描く。著者は「海の都の物語」と違って地中海全体を眺めたのが「ローマ亡き後の地中海世界」だとするが、本書も西地中海、つまり北アフリカから繰り出すイスラム教徒の海賊と迎え撃つ西欧キリスト教諸国が物語の中心。海が苦手のトルコは西欧への攻撃のために海賊を支援し、遂には赤ひげ等をトルコ海軍総司令官に任命する。赤ひげがフランスに国賓として滞在中にも海賊業に励んでいたのには驚いた。迎え撃つ西欧諸国側も傭兵が活躍する。スペイン海軍総司令官となったアンドレア・ドーリアがその筆頭。ドーリア対海賊の戦いが本書中盤のハイライト。西欧連合の足並みが揃うことは稀で、名将ドーリアが奇妙な負け方をしたプレヴェザの海戦とスペイン王のアルジェ遠征失敗が響き、海賊にやられ放題の時期を迎える。名もない人の苦しみが続く様は哀れだ。しかし、トルコが本格的に西地中海に遠征したマルタ島攻撃を退け、レパントの海戦で西欧が勝利してからは、西欧が自信をつけ、さらに地中海の地政学的重要性の低下もあって、海賊は下火になる。レパント後の空気を伝えるエピソードが良い。 本書は森を語り、樹(例えば東地中海での攻防やレパントの海戦の詳細)のうち著者の既刊書に譲れるものは譲っている。本書で一連の歴史に初めて接する人は戸惑うかもしれないが、まずは大きな時代の流れを掴んで、巻末附録二掲載の本を読むとよいだろう。それらの本を読んでいる人にも樹の各々が森のどこに位置するかを確認でき、マルタ島攻防記等、初めてじっくり読む話もあって、やはり本書はお薦めだ。オスマン・トルコの歴史への誘いにもなるだろう。 |
 ローマ亡き後の地中海世界(上) |
この上下間に渡る大著を一言で言えば、
「ヨーロッパ対アラブ海賊の戦いの歴史」。 最終的にヨーロッパ世界が反撃に出るとはいえ、記述の大半はいかにヨーロッパ人たちがアラブ人に苦しめられたかということだ。 『ローマ人』の爽快さと比べると、読んでいて少々気が重くなる作品でもある(『ローマ人』も末期のほうは、同じように気が滅入る場面が多かったが・・・)。 塩野さんがこんなことを意識していたかどうかはわからないが、本書を読んで私が一番強く思ったのは、 「歴史における強者と弱者の立場の逆転」 ということ。 ここ100年ほどのヨーロッパ世界とアラブ世界の関係を見ていると、アラブ人の国土を勝手に分割したり、ユダヤ人の入植を認めて混乱の火種を蒔いたりと、ヨーロッパ側の傍若無人さを非難したくなる人が多いだろう。 事実、私もそうだった。 だが本書で、いかに中世のヨーロッパがアラブ世界からひどい仕打ちを受けていたかを知ると、 「それもまたやむなし」 などと思ってしまうのだから、自分でも怖くなってしまう。 ちょっと重苦しい気分になるが、この時代のことを扱った本が少ないこともあり、いろいろ発見の多い一冊でもある。 |
 ローマ人の物語 (1) ― ローマは一日にして成らず(上) 新潮文庫 |
以前から気になっていたシリーズだが、ついにこの「ローマ人の物語」を読みはじめている。もともと、歴史には疎い方で、特に世界史のことはごく基本的なことも知らない。大事だとわかっていても、勉強のようにつまらなく感じてしまうのであった。
ところが、この塩野七生氏の著作は文句なしにおもしろく読める。基礎知識がなくても、わかりやすい。そして、人間や社会の本質を理解する上で実にためになる知恵がつまっているのである。おもしろい理由のひとつは、人間のひとりひとりに焦点をあてて丁寧に描かれていることだろう。そして、その見方が肯定的なのがよい。 現在シリーズの半分ほど読んだところだが、どの巻も粒ぞろいで退屈することなく読みすすめられている。 |


![[MAD]秋姫すももの憂鬱(ななついろ★ドロップス) ななついろ★ドロップス](http://img.youtube.com/vi/J0EtCT7xT08/1.jpg)






